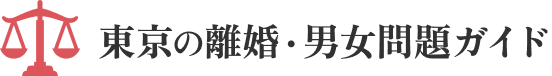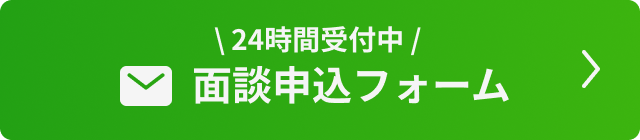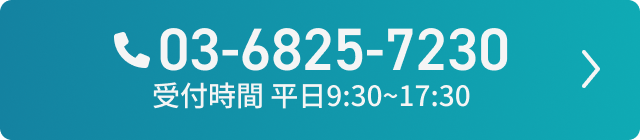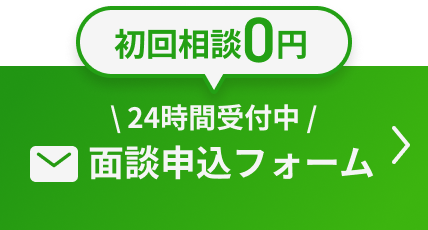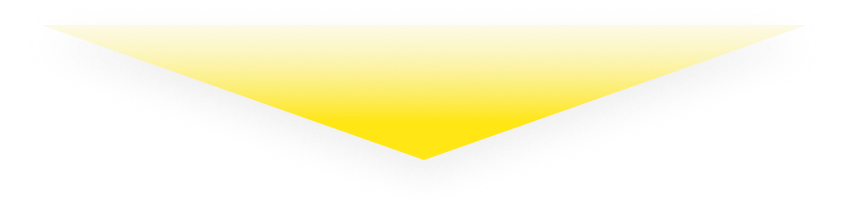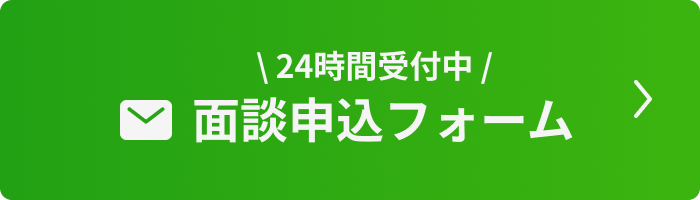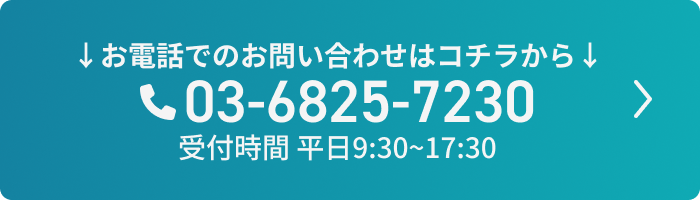もし親権を取れなかったら、子どもと離れ離れになるかもって考えると怖くて…
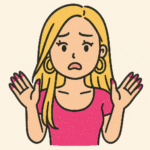
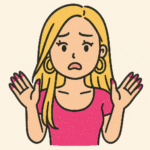
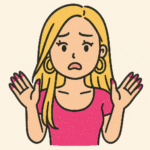
夫も『親権は譲れない』って言い出して、もうどうすればいいか分かりません…
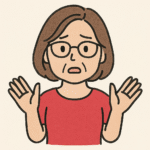
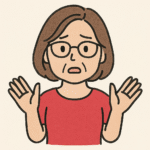
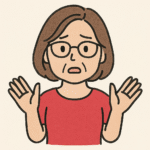
自分が親権を持ちたいが、相手(夫)も主張してきている…
離婚を考える上で、「親権」は最も大きな不安要素のひとつです。特に、子どもと一緒に生活を続けたいと思っている方にとって、親権を巡る争いは精神的な負担が大きくなります。



本記事では、親権と監護権の違いや、親権を誰が持つかを判断する際に裁判所が重視するポイントについて、離婚に強い弁護士が分かりやすく解説します。「親権を取れるのはどんな人?」「母親の方が有利って本当?」といった疑問にもお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
離婚でよくある「親権」と「監護権」の違いとは?弁護士がわかりやすく解説


離婚をする際、未成年の子どもがいる夫婦は、どちらを「親権者」にするかを必ず決める必要があります。しかし、「親権」と「監護権」の違いが分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。



ここでは、離婚や子どもの親権について弁護士に相談する前に知っておきたい基礎知識として、親権の内容と監護権との違いを分かりやすく整理します!
親権は主に3つの権利に分かれます
1:身上監護権
子どもの生活全般に関する管理・監督(しつけ、教育、医療など)を行う権利
2:法定代理権
子どもに代わって契約や手続きを行う法的な代理権
3:財産管理権
子ども名義の財産を保護・管理する権利
この3つをまとめて「親権」と呼び、原則として離婚時には父母のいずれか一方が単独で持つことになります。
監護権とは?親権との違いは?【弁護士が解説】
一方、「監護権」とは、子どもと一緒に生活し、実際に育てる権利・義務を指します。場合によっては、親権を父親が持ち、監護権を母親が持つというように、分けて定めることも可能です。



このように、親権と監護権はセットと考えがちですが、必ずしも同じ親が持たなければならないわけではありません。離婚後の生活を見据えて、どちらの親がどの権利を持つか、柔軟に決めていくことが大切です。
離婚後の生活を見据えて、どちらの親がどの権利を持つか、柔軟に決めていくことが大切です。
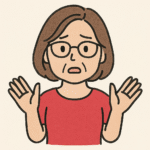
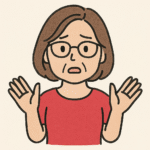
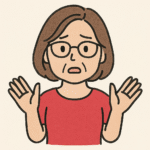
自分は親権を持てるの?
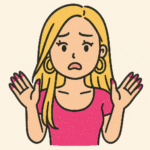
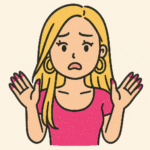
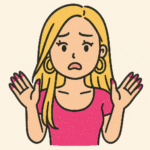
監護権だけでも確保できるの?
といった悩みは多くの方が抱えるところです。不安な方は早めに弁護士に相談することで、自分の希望を叶えるための方針や交渉方法が見えてくるかもしれません。
親権・監護権の決定に影響を与える4つの要素


親権者が夫婦の話合いで決まらない場合は、調停や裁判所での手続により解決を図ります。その際、家庭裁判所調査官による調査が行われ、以下の4つの要素が考慮されます。
1. 調査官による子供の面談
家庭裁判所調査官が、子供の心理的影響や生活状況を確認するために、家庭訪問や面談を行います。子供の気持ちや親との関係性、環境の安定性などが調査されます。
2. 子供の意見聴取
15歳以上の子供の場合、裁判所は子供の意見を聞くことが法律で義務付けられています。15歳未満の子供に対しても、調査官が質問を工夫しながら意見を確認します。
3. 兄弟姉妹の育成環境
兄弟姉妹はできる限り一緒に育てられることが望ましいとされており、親権決定の際にも考慮されます。
4. 子供の適応状況
子供が学校や地域にどの程度適応しているかが重視されます。特に転校の可能性がある場合、子供の適応力や環境の変化に対する影響が考慮されます。


これらの要素は、親権や監護権をどちらが持つかを判断するうえで非常に重要なポイントです。特に、子どもの生活環境や心理的な安定が最優先される傾向にあるため、親として何を準備し、どのように対応すべきかを知っておくことが大切です。
親権をめぐる争いは感情的にも複雑になりがちですが、家庭裁判所での判断基準を理解し、冷静に対応することが結果に大きく影響します。不安な場合は、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスや準備を進めることが、後悔しないための第一歩です。
親権はどうやって決まる?離婚時に知っておきたい4つの判断基準と弁護士の視点
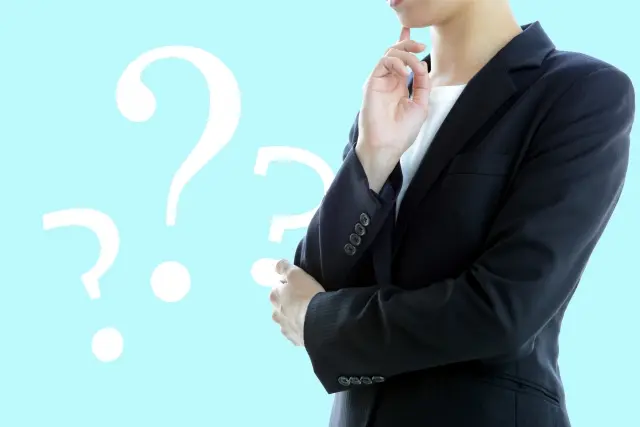
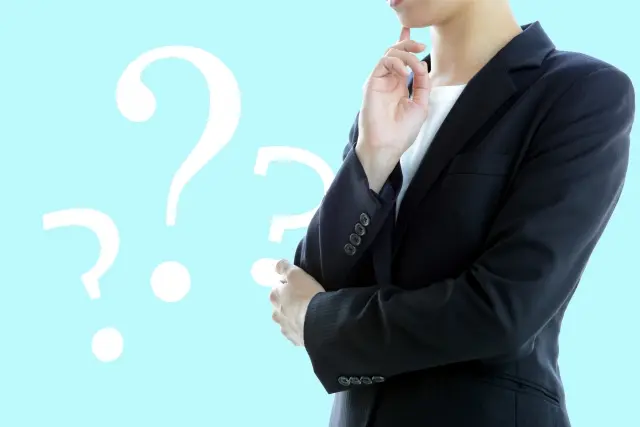



今まで私が子育てをしてきたのに、親権を取れなかったらどうしよう…
離婚を考えたとき、親権をめぐる不安は多くの方が抱える深刻な悩みです。調停や裁判に発展した場合、親権は「どちらがふさわしいか」を家庭裁判所が客観的に判断します。その際、「子どもにとって最も良い環境とは何か」を基準に、いくつかの要素が重視されます。
ここでは、親権がどうやって決まるのか、その具体的な判断基準と、弁護士の視点から見た重要なポイントを解説します。



親権の取得を真剣に考えている方は、ぜひ参考にしてください!
1. 継続的に子供を養育している親
子供の安定した生活が最優先されるため、日常的に子供を養育している親が有利になることが多いです。特にこれまでの養育実績が重視されます。
2. 経済的・精神的な安定
親が経済的に自立し、精神的にも安定していることは、子供にとっての安定した養育環境を提供するために重要です。収入や家族からのサポートも考慮されます。
3. 子供と過ごす時間の確保
親権者として、親が子供と十分な時間を過ごせるかどうかも重要です。就労状況や家庭環境が整っているかが評価されます。
4. 現在および将来の養育環境
すでに別居している場合は、現在の生活環境が子供にとって安定しているかどうかが評価され、将来の養育環境がどれだけ安定しているかを示すことが大切です。


親権の決定においては、親の希望や主張だけでなく、「子どもの安定した生活環境」が最も重視されます。
これまでどれだけ子どもと向き合ってきたか、今後どのように育てていけるかを、具体的な根拠をもって示すことが求められます。
「自分に親権が認められるのか不安…」と感じている方こそ、早い段階で弁護士に相談し、裁判所がどこを重視するのかを理解したうえで準備を進めることが大切です。
一人で抱え込まず、専門家と一緒に冷静に対応していくことで、子どもとのこれからの生活をしっかり守っていきましょう。
なぜ母親が親権に有利とされるのか?3つの視点で弁護士が簡単に解説!


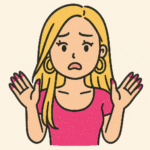
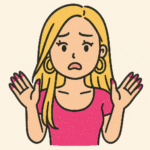
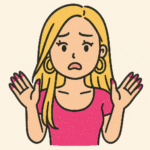
親権はやっぱり母親の方が有利って聞くけど…それって本当なの?
実際、裁判所で親権者として母親が選ばれるケースは多いのが現実です。ただし、それは「母親だから」という理由ではなく、これまでの育児の実績や、子どもにとっての安心感が総合的に評価されているためです。
ここでは、なぜ母親が親権で有利とされやすいのか、その背景や裁判所の判断傾向について、弁護士の視点から3つに絞ってわかりやすく解説します。



「本当に親権を取れるのか不安…」という方は、ぜひ参考にしてください!
1.継続的な養育者が母親であることが多い
親権の判断では、日常的に子どもを育ててきた実績が重視されます。実際には、これまでの育児の大半を担ってきたのが母親であるケースが多く、自然と母親が親権を得やすい傾向にあります。
2.幼い子供にとって母親の存在が重要視される
とくに子どもが幼い場合、母親の愛情や身体的・精神的なつながりが重要視される傾向があります。裁判所も、子どもの健やかな成長のために「母性の継続性」が望ましいと判断することが多いです。
3.子供自身が母親を選ぶことが多い
子どもがある程度成長している場合、その意思も考慮されます。多くのケースで、子ども自身が母親を選ぶ傾向があり、これも母親に親権が認められる一因となっています。
まとめ:親権で悩んでいる方へ、いま大切にしてほしいこと


親権をめぐる問題は、子どもの将来にも深く関わる重大なテーマです。
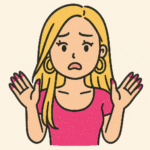
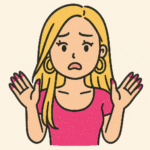
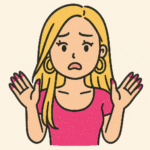
親権を取れなかったら子どもと離れ離れになってしまうかも…
という不安は、多くの方に共通しています。しかし、裁判所は一貫して「子どもにとってどちらの親と過ごすのがより良い環境か」という視点で判断しています。単なる“母親か父親か”ではなく、これまでの育児の実績や、現在・将来の生活環境、子どもとの関係性といった複数の要素を総合的に見て決定されます。



もし今、親権について不安や悩みを抱えているなら、一人で抱え込まず、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。
あなたの状況を整理し、どんな準備が必要か、どのように主張すべきかを一緒に考えることで、後悔のない選択ができるはずです。
大切なお子さんとのこれからの生活を守るために、まずは一歩踏み出してみてください。私たちは、その一歩を全力でサポートいたします。


監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。


監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。